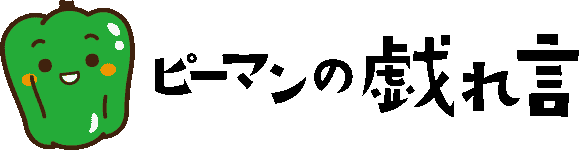シャドーAIとは?
「シャドーAI(Shadow AI)」とは、企業のIT部門やセキュリティ部門の承認・管理を受けることなく、従業員が個人の判断で業務に利用するAIツールやシステムを指します。これは、既存の「シャドーIT」(企業が把握していないIT機器やソフトウェアの利用)のAI版とも言える現象です。
生成AIの急速な普及に伴い、ChatGPTやGeminiのようなチャットAI、画像生成AI、文章作成AI、AIによるデータ分析ツールなどが手軽に利用できるようになったことで、従業員が「業務効率を上げたい」「もっと便利なツールを使いたい」という善意から、会社の承認を得ずにこれらのAIツールを使い始めるケースが増えています。
例えば、以下のようなケースがシャドーAIに該当します。
- 営業担当者が顧客とのメールのやり取りを効率化するために、ChatGPTに顧客情報を入力して返信文を作成する。
- マーケティング担当者が新しい広告コピーを考案するために、生成AIに過去のキャンペーンデータを入力する。
- ソフトウェアエンジニアが、個人のAIアカウントを使って定型コードを生成したり、レガシーコードをリファクタリングしたりする際に、意図せず機密コードをパブリックモデルに貼り付けてしまう。
シャドーAIが特に注意すべきなのは、AI特有のデータ処理や、AIが生み出す情報、そしてその判断プロセスに関連する固有のリスクがある点です。
企業が直面するシャドーAIの主なリスク
シャドーAIは、企業の生産性向上やイノベーション加速の可能性を秘める一方で、IT部門やデータガバナンスチームの監視外で利用されるため、深刻なセキュリティ、コンプライアンス、運用上の課題をもたらします。
主なリスクは以下の通りです。
1. 機密情報・個人情報の漏洩リスク
- 最も深刻なリスクの一つです。従業員が未承認のAIツールに企業の機密情報(新製品情報、企業戦略、財務データなど)や顧客の個人情報(氏名、連絡先、購買履歴など)を入力すると、その情報がAIの学習データとして利用され、意図せず外部に漏洩してしまう可能性があります。
- AIサービスによっては、入力されたデータがモデルの学習に利用されることを利用規約で明記している場合があります。これにより、同じサービスを利用する他のユーザーへの回答に、自社の機密情報が含まれてしまうといった事態も起こり得ます。
エビデンス: 従業員の約半数が会社に無許可で生成AIを業務に利用しており、情報漏洩のリスクが指摘されています。(参照: AI経営総合研究所 – シャドーAIのリスクと対策とは?)
2. 著作権・知的財産権の侵害リスク
- AIが生成したコンテンツ(文章、画像など)が、既存の著作物と酷似していた場合、著作権侵害に発展する可能性があります。
- 特に、商用利用が禁止されているAIサービスで生成した画像を、業務で利用してしまうケースは非常にリスクが高いです。従業員が各ツールの利用規約を把握していない場合、製品パッケージやマーケティング資料などで意図せず著作権を侵害してしまう恐れがあります。
3. 不正確な情報(ハルシネーション)による業務判断ミス
- 生成AIは、あたかも事実であるかのように、誤った情報や存在しない情報を生成する「ハルシネーション」を起こすことがあります。
- 従業員がシャドーAIが生成した不正確な情報を鵜呑みにして業務上の重要な意思決定を行った場合、企業の信頼性低下や経済的損失につながる可能性があります。
- また、偏見を含むコンテンツや差別的な表現が生成され、それが社内外で使用されると、企業イメージの低下や炎上につながるリスクもあります。
4. セキュリティ対策の遅延と脆弱性
- IT部門が管理・把握していないAIツールが使われると、トラブル発生時やセキュリティインシデント発生時の対応が遅れてしまいます。どのツールで、どのようなデータが、どのように扱われているか不明なため、迅速な調査や対処が困難になります。
- 未承認のAIツール自体にセキュリティ上の脆弱性がある場合、それが企業のシステム全体への攻撃経路となる可能性も否定できません。
5. コンプライアンス違反
- GDPR(EU一般データ保護規則)やCCPA(カリフォルニア消費者プライバシー法)など、個人情報保護に関する各国の規制に違反するリスクがあります。特に顧客データや機密情報を無許可のAIツールに入力した場合、法的な問題に発展する可能性があります。
- 社内規定や情報セキュリティポリシーに違反する行為であり、内部統制の観点からも問題となります。
シャドーAIに対する効果的な対策

シャドーAIのリスクを完全にゼロにすることは難しいですが、適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑え、AIのメリットを享受することが可能です。
1. 社内ガイドラインの策定と周知徹底
- AI利用に関する明確なルール作り: 従業員がどのAIツールを、どのような目的で、どのように利用して良いのか、または利用してはいけないのかを具体的に定めたガイドラインを策定します。
- 入力データの制限: 機密情報や個人情報の入力禁止、著作権保護されたコンテンツの利用制限などを明記します。
- 生成物の取り扱い: AIが生成した情報のファクトチェックの義務付け、商用利用前の著作権確認ルールなどを定めます。
参考: 一般社団法人日本ディープラーニング協会が公開している「生成AIの利用ガイドライン」などが参考になります。(エビデンス: HYPER VOICE – 約半数が経験あり!?シャドーAIが抱えるリスクや対策を解説)
2. 従業員のAIリテラシー向上とセキュリティ教育
- リスクの啓発: シャドーAIがもたらす具体的なリスク(情報漏洩、著作権侵害、ハルシネーションなど)について、具体的な事例を交えながら従業員に教育・啓発を行います。
- 適切な利用方法の指導: 安全なAIツールの選び方、プロンプトの入力時の注意点、生成物の確認方法などを指導します。
- 定期的な研修: AI技術の進化に合わせて、定期的に研修を実施し、従業員のリテラシーを継続的に向上させます。
3. 社内で安全に利用できるAIツールの導入と提供
- 公式ツールの提供: 従業員が業務でAIを利用したいというニーズに応えるため、セキュリティ対策が施され、企業が管理できる公式のAIツール(例:Microsoft Copilot for Microsoft 365など、企業向けにカスタマイズされたAIサービス)を積極的に導入・提供します。
- API連携の活用: 機密情報を学習データとして利用されないよう、API連携によってAIサービスを利用できる環境を構築します。これにより、入力データがAIモデルの学習に利用されず、情報漏洩のリスクを低減できます。(エビデンス: リコーのAI – 生成AIのセキュリティリスクとは?)
- 利用状況の可視化: 従業員がどのAIツールを、どの程度利用しているかを把握できる仕組みを導入し、シャドーAIの実態を可視化します。
4. セキュリティ対策の強化とガバナンス体制の構築
- データ保護の強化: AIが学習・蓄積するデータの保存先を暗号化したり、通信経路を保護したりするなど、データの暗号化と保護を徹底します。
- アクセス制御: AIツールへのアクセス権限を適切に管理し、不要なアクセスを制限します。
- AIガバナンスの確立: AIの導入から運用、廃棄までのライフサイクル全体で、リスク管理とコンプライアンスを確保するための統制(ガバナンス)体制を構築します。これは、AIのメリットを享受しつつ、リスクを抑制するための重要な取り組みです。(エビデンス: Zscaler – シャドーAIとデータ セキュリティ)
- 継続的な監視: AIツールの利用状況や、新たなAIサービスの登場を継続的に監視し、リスクを早期に発見・対処できる体制を整えます。
まとめ
シャドーAIは、現代の企業が直面する新たな、しかし避けられない課題です。従業員の生産性向上やイノベーションの推進というAIの恩恵を享受するためには、AIの利用を一律に禁止するのではなく、そのリスクを正確に理解し、適切なガイドラインの策定、従業員教育、そして安全なツールの提供とガバナンス体制の構築を通じて、AIを「影」から「光」へと変える取り組みが不可欠です。これにより、企業はAIの力を安全かつ効果的に活用し、競争優位性を確立することができるでしょう。
関連記事
参考情報
- Rentec Insight:シャドーAIとは?生成AIの業務利用によるリスクについて解説
- zendesk:シャドウAIとは?未承認AIのリスクと企業が取るべき対策
- 生成AI活用ナビ:シャドーAIのリスクと対策とは?会社に”無許可”で生成AIを業務に利用している実態が明らかに